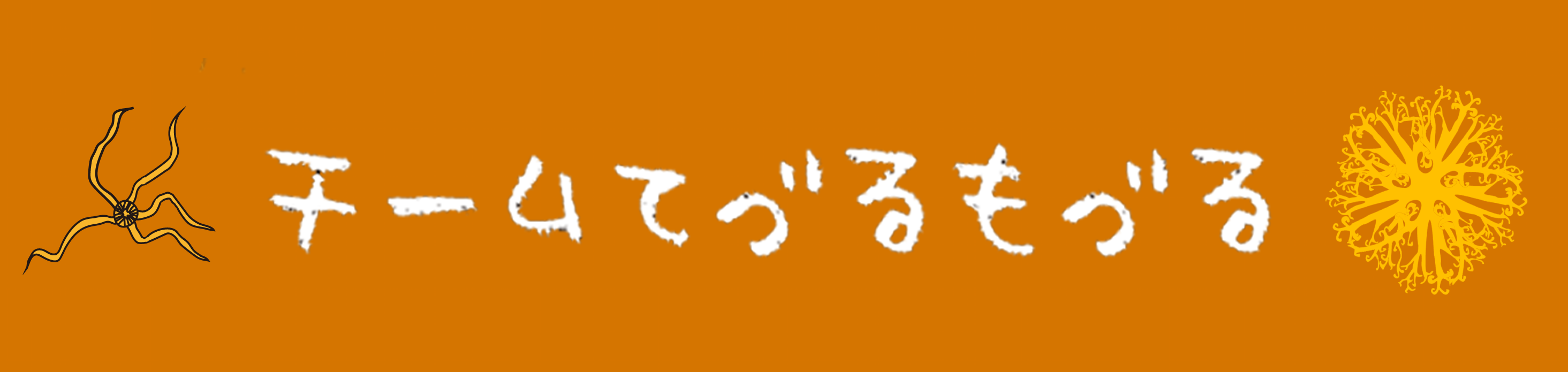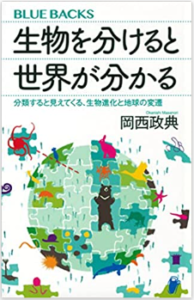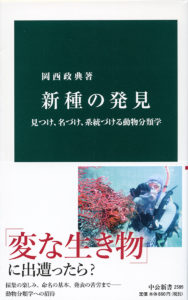せっかくの機会なので,
今回はたくさん生物写真を紹介しましょう.
普段何気なく見ているつもりのサンゴですが,
よーく拡大してみると,一つ一つのセクションから,
小さなイソギンチャク状の触手(ポリプ)が伸びており,
群体性の刺胞動物であることがよくわかります.
こちらは,白黒パンダ模様のサンゴではありません.
右側は死んでしまっているようです.
生きている部分のポリプは, こんな風に非常に元気であります
こちらは,遠目に見てもポリプがもさもさしているのがわかります.
近づいてみても,一つ一つの触手が長いのがわかりますね.
一見,ほとんど石のように見えるサンゴも,よーく近づくと...
表面に小さなポリプが触手を伸ばしています
こんな風に,一口にサンゴと言っても,いろいろな形があるんですね.
なかなかサンゴのポリプをうまく写した写真を持っていなかったので,
今回はこの写真が取れだけでも満足です
しかしわれらが棘皮動物も負けてはいません.
海草の間に突如として出現したマンジュウヒトデ.
思わず多孔体を接写してしまいました.
よーく見ると,なんだか網目模様が見えます.いったい,これは何なのか.
標本だけからではわからないことに遭遇できるのも,フィールドワークの魅力に一つですね
ちなみに多孔体は,棘皮動物の肝とも言える器官で,
読んで字のごとく穴凹だらけのこの骨片の板を通して,
体の中の水が通る管(水管系)へ海水が入っていきます.
これがなければ,棘皮動物は管足を動かせないので,
食事はおろか,移動や呼吸にも支障をきたします.
逆に言えば,水管系はそれだけ棘皮動物にとって重要な器官ということです.
しかし,でかい!これだけ巨大な体になれるのも,
実は水管系のおかげなのです
と,結局は棘皮動物のお話になってしまっているのでした.
続く.