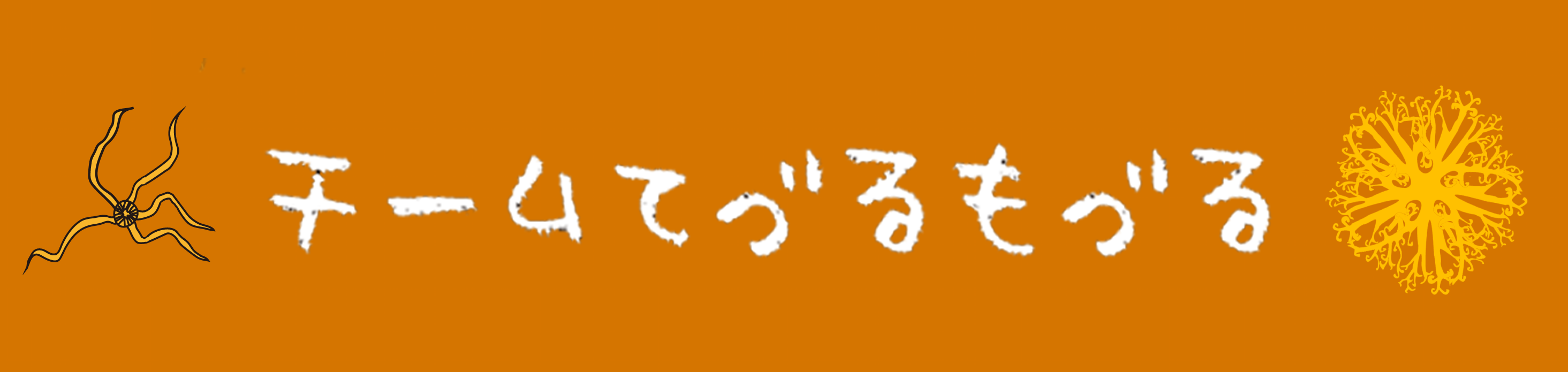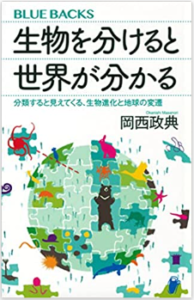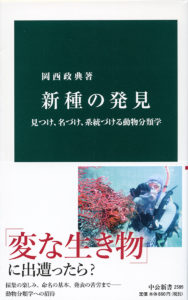一番手はフナムシの行動実験の発表
フナムシのジグザグ行動の検証ですが,
曲がり角にぶつかった際,
初めに左右の触覚どちらかが当たったのと反対の方向に曲がるのでは?
という仮説のもと,実証に取り組んでくれました.
「触覚に注目した実験は初めてだ」
先生方からも意見が飛び交います.
フナムシの行動実験二つ目です.
この班では,明暗が行動に及ぼす影響に注目しており,
迷路にカバーを掛けてみるなどのユニークな実験に取り組んでいました.
「それを検証するためには,他にどんな実験をすればいいと思う?」
学生の意見を引き出そうとする質問です.
お次はpHがウニの受精に与える影響に関しての実験です.
受精卵から,精子を誘引する物質(彼らは「卵エキス」と読んでいた)
が分泌されており,その物質の影響が大きいのではないかということを検証しようとしていました.
こちらも非常にユニークな着眼点でした.
次は巻貝の生理学実験です.
色々な塩の組成で巻貝の出殼反応を試しましたが,
どの塩の組み合わせが本当に巻貝に認知されているのかが詰めきれなかったようです.
このような化学的な実験は,微量な化学物質の差で実験結果が変わってしまいます.
そのような指摘にも耐えうる高精度な実験を行ってくれました
締めは巻貝の出殼反応第二弾です.
普通,この実験は巻貝の反応について,殻から出て動き回る,
という行動をポジティブな反応のMaxとするのですが,
彼はそのまま観察していると,突っついても動かなくなる
(「馬鹿になる」と表現されていました)ことを見出しました.
実は今回実験に使った塩化マグネシウムは海産無脊椎動物の麻酔薬によく使われています.
彼が見出したこの馬鹿になる反応は,
まさに塩化マグネシウム溶液に漬けた時によく現れる傾向が出ていました.
目の付け所は面白かったのですが,
実験方法の詰に甘い部分があり,西田先生から指導が入っていました.
自由課題実習の醍醐味は,
多様な自然環境の中から興味深い題材を発掘することにも意義はありますが,
それ以上に,自分が選んだ課題をいかに科学的に検証していくか,
という方法を学んでもらえるところに大きな意義があります.
その指導を行うためには,
普段の研究生活の中で常に科学的な思考を養っていかなくてはならないのだということを,
私たちも学ばせていただきました.
当たり前の事ですが,日々の雑務にも追われつつも,
この感覚をキープしなくていはいけませんね.
ちなみに,16:00から発表をはじめて,終了したのは19:00でした
みなさん本当にお疲れ様でした